
回収された砲弾のようなもの(提供:北海道警)
驚きの発見と避難騒動
9月29日、北海道恵庭市で住宅の車庫から砲弾のようなものが見つかり、周囲の住民5人が避難しました。見つかったのは直径約9センチ、全長約25センチの金属製の物体。持ち主の男性は「40年以上前に新築祝いとして知人から譲り受け、庭に埋めていたものを最近掘り起こした」と説明しています。現在は陸上自衛隊が安全確認と処理にあたっています。
「新築祝いに砲弾」という時代錯誤の驚きはありますが、実際にこうした“戦時由来の不発弾や軍需品”が個人宅や倉庫から出てくるケースは、今でも各地で報告されています。
戦後から今に残る“爆弾の爪痕” ~ 過去の発見例から学ぶ
日本では戦後80年を経た現在でも、不発弾や砲弾・焼夷弾などが年に複数件、主に建設・解体・河川工事の現場などから出土しています。
例えば、広島大学霞キャンパスでは、敷地内で2度目と思われる不発弾が発見され、警察がその日のうちに無事回収を完了した例もあります。
また、名古屋市の中心部では、太平洋戦争末期に投下されたと見られる 全長120センチ/直径36センチ/約250kgの焼夷弾 が工事中に発見され、千人規模の避難が行われた例もあります。
さらに、沖縄では不発弾処理中に爆発事故も発生。自衛隊員が軽傷を負う事態も実際に起きています。
これらの事例は、不発弾の取り扱いがいかに慎重を要するかを物語っています。発掘・処分過程にはさまざまなリスクが潜んでおり、技術と警戒が不可欠です。
参考リンク
もし爆弾のようなものを見つけたら
今回のニュースから考えるべきは、「もし自分が爆発物らしきものを見つけたらどうするか」という点です。万一に備えて、基本的な対応を押さえておきましょう。
❌ やってはいけないこと(絶対に触らない/操作しない)
- 決して力を加えたり、叩いたり、揺らしたりしない
- ハンマーなどで叩く・金属棒で突くなどの行為
- 火気・電気機器(発光器具、スマホライトなど)を近づける
- 移動を試みる、持ち帰る、包み込むような行為
✅ やるべきこと(速やかな安全確保と通報)
- その場を離れる(最低半径数十メートルは距離を取る)
- 110番通報/警察に連絡
- 発見場所、形状・大きさ・色・材質の特徴を伝える - 近隣住民や家族へ知らせ、避難促す
- 現場の保存:立ち入らず、足跡を残さず、他者の接近を防ぐ
- 警察・自衛隊の指導に従う
- 指定区域での立ち入り規制や封鎖指示に応じること - その後の情報確認
- 地域の避難情報・処理スケジュールなどを市町村告知で確認
こうした対応は、不発弾だけでなく「不審な金属塊」「発火性の疑われる物体」など、正体不明の物体すべてに応用できます。
なぜ今でも残っているのか、そしてそこから問われる責任
恵庭市の事例をきっかけに、私たちは日本社会に残る「戦争の痕跡」と「現代の安全管理のギャップ」を再認識するべきです。
日本国内には、沖縄を中心に 未爆炸弹薬(不発弾・砲弾)が多数存在する という推計もあります。
戦後80年を超えた今でさえ、毎年数百件規模で発見され、処理されており、完全処理にはあと何十年もかかるとされる地域もあります。
また、処理中の事故報道(沖縄の保管庫爆発など)は、自衛隊側の技術管理・安全対策にも問を投げかけています。
国・自治体・工事業者・住民それぞれが、不発弾のリスクを認識し、安全対策に参加する姿勢が求められる時代になっていると言えるでしょう。
恵庭市の事例は「まさか家庭に砲弾が」という驚きのニュースでしたが、現実には戦後から数十年経った今でも、全国で年に数十件の不発弾処理が行われています。ニュースを他人事として笑って終わるのではなく、もし自分の近くで見つかったらどうするか、家族で話しておくのも安心です。
参考リンク・引用元
- livedoorニュース「北海道恵庭市の住宅で砲弾発見」
https://news.livedoor.com/article/detail/29673282/


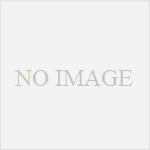
コメント